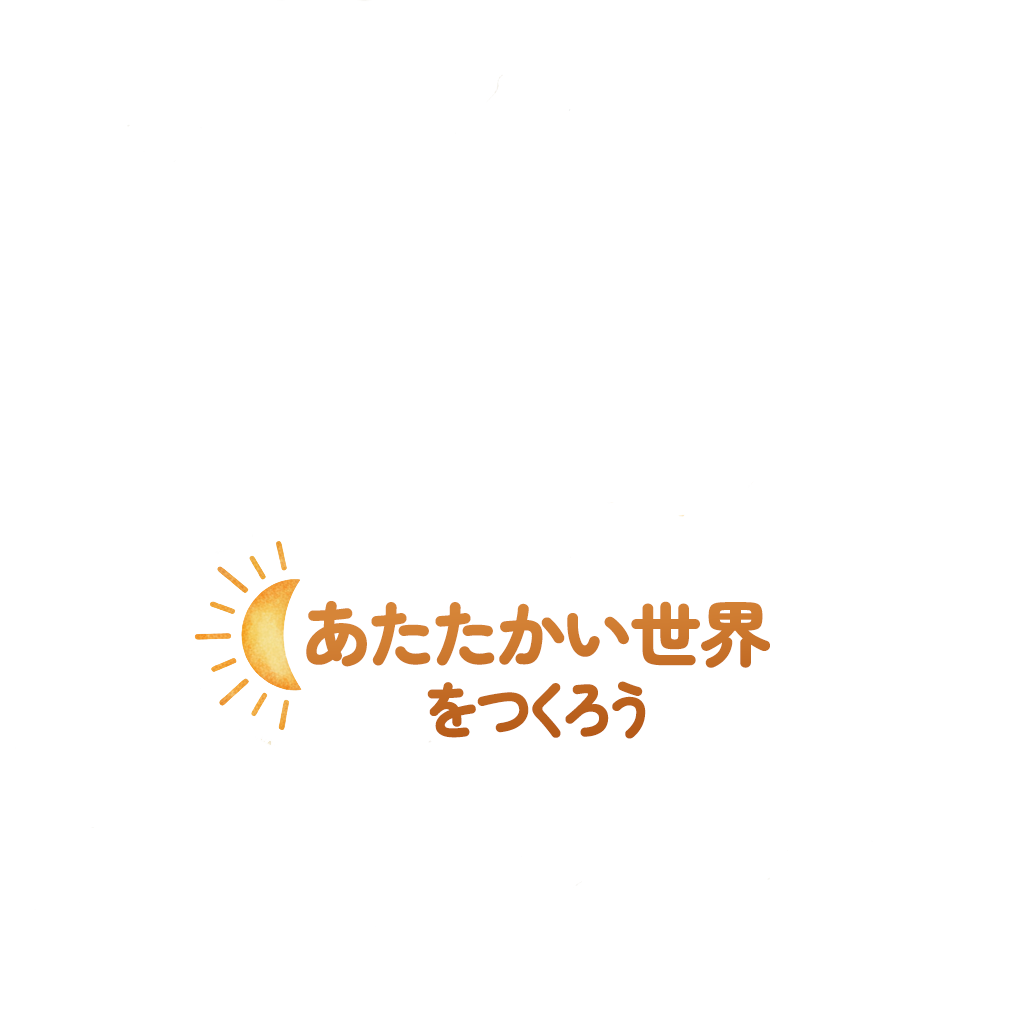あなたを疲れから救う休養学2ー攻めの休養

休養学によると、単に寝ることや体を休めることが休養ではなく、あえて自分にちょっと負荷をかけることが提唱されています。「疲れているのにさらに負荷をかけるなんてとんでもない」と思われるかもしれません。
でも、あえて軽く負荷をかける→その後休息することで、逆に活力が高まることが分かっています。例えば筋トレの場合、重いものを持ち上げるなどして負荷をかけて1回筋繊維を壊します。その後、2,3日トレーニングせずに休養に専念すると、トレーニング前よりも筋繊維が肥大しているのです。
同じように、休養も単に寝るのではなく、あえてなにかの「活動」をすることで、少しの負荷をかけることで、逆にリフレッシュしたり、活力を得ることができるということです。休養学では7つの休養タイプが提唱されていました。
- 休息タイプ
- 運動タイプ
- 栄養タイプ
- 親交タイプ
- 娯楽タイプ
- 造形・想像タイプ
- 転換タイプ
それぞれ紹介しますね。
1.休息タイプ
活動を停止して休んだり睡眠を取る。一般的な休息のイメージに近い
2.運動タイプ
適度な運動をすると血液の流れが良くなり、老廃物の除去やリンパの流れが良くなるので疲労軽減につながります。お風呂に入ることも運動の1種です。体を温めるだけでなく、水圧がかかるのでマッサージを受けるのと同じ効果が期待できます。
3.栄養タイプ
バランスの取れた食事をすることは大切ですが、本書では「食べないこと」「量を減らすこと」が提唱されています。現代人は、栄養不足の害よりも「食べすぎ」の害のほうが大きくなっているからです。消化器系を休ませて老廃物をデトックスすることで体を休めることができます。
マウスを使った実験でも、満腹まで食べるマウスよりも、腹8分目のマウスのほうが寿命が1,5倍伸びたという研究結果もあるようです。腹8分目が健康にいいということですね。
4.親交タイプ
友達と会話したり、家族や恋人とハグしたり、スキンシップを取ることでストレスを解消していきます。ふれあう相手は動物でも構いません。スキンシップやハグをする相手がいなくても、職場の人と明るくあいさつを交わすとか、近所の人や店員さんに「おつかれさま」という声がけをすることも親交の一種です。
もちろん、人と会うほうが疲れるタイプの人は無理に親交する必要はない、自分を責めなくて良いと書いてくれているのも救いです。でも、そういう人でも、マンションのエレベーターで乗り合わせた人にちょっと会釈するとか、困っている人に手を差し伸べるなど、ちょっとしたことを行なってみることはできます。
また自然に触れるのも親交の1種。最近は「森林医学」という分野で森林浴の効果が科学的に研究されているようです。研究によると、樹木はフィトンチッドという揮発性の物質を出していて、それに含まれるテルペン類という科学物質を鼻から吸い込むことで体に良い影響を与えるとのことです。森林に行くことでセロトニンという精神を安定させるホルモンも脳内で出るようになります。
5.娯楽タイプ
趣味嗜好を追求する方法です。好きな音楽を聞く、映画を見る、ゲームをする、推し活をする、読書、習い事をするなど、何でもOKです。ただし、ハマりすぎないように注意は必要です。
6.造形・想像タイプ
絵や詩を書く、作曲する、日曜大工で何かを作るなど、創作活動全般です。創作が得意でなくても、地図や時刻表を眺めて旅行している気分になったり、美術館で絵を鑑賞して作者の気持ちを想像したりでも大丈夫。好きなアイドルのことを考えるなど好きなことを空想するのもいいですね。
7.転換タイプ
まわりの環境を変えることです。環境をかえるというと、引っ越しや転職をイメージするかもしれませんが、洋服を着替える、部屋を模様替えする、庭に花を植える、整理整頓するなども環境の変化になります。転換行動の代表例は旅行です。普段とは全く違う環境に身を置くのでとても良い休養になります。
7つの休養を組み合わせれば、休み方は無限大!
大切なのは、7つのタイプの休み方を組み合わせること。もちろん、単体で行なっても効果はありますが、組み合わせて行なうことで何倍もの疲労回復効果を期待できます。
例えばスープを作って飲むとしましょう。スープを作ること自体が造形・想像タイプの休養ですが、それを飲むことで消化器をやさしく癒やす栄養タイプの活動にもなります。また家族や友達と一緒に飲むと、会話が生まれ親交タイプにもなります。スープを保温ジャーに入れて公園に出かければ、公園まで歩く運動タイプ、場所が変わる転換タイプの休息にもなります。さらに自然との親交にもなりますね。
こんな感じでいくつかの休養タイプを組み合わせることでさらなる効果を期待できます。組み合わせはアイディア次第で無限大。普段なにげなくやっていることも「組み合わせてこういう休養にならないかな」と意識してみると、いろいろな休養法が見つかっていくかもしれませんね。
現代は肉体労働から頭脳労働の比重が高まり、テクノロジーの普及で24時間仕事の連絡が来たり情報が入ってくる世の中になりました。だからこそ、休養も「寝て休む」という体の休養だけでなく、心の休養の重要性が高まっているかもしれませんね。
みなさんもよい休養を取って、活力を取り戻してください!